
|
(TEC換算で2〜4×10 16elec./m2)程度である。
この受信装置を用いて、1990年(太陽活動極大期)に国内3ヵ所(沖縄、小金井、水沢)において電離層遅延観測を実施した。図3.3.2.2−2はその位置関係を示している。
図3.3.2.2−2 TEC観測点位置関係
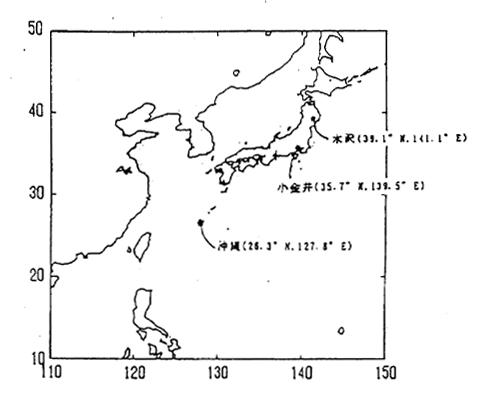
図3.3.2.2−3は約2週間の連続観測結果を示しており、GPS衛星視線方向のTEC測定値を天頂方向へ換算(電離層を同心球層状として仮定)したものである。
また、図3,3.2.2−4(1)、(2)は図3.a2.2−3のうちの1日の観測結果を示すものである。これらの図から、中緯度においては、
・低緯度ほど電離層の活動が盛んであること
・沖縄付近の低緯度では、方位角依存性(南方異常)があること
などがわかる。
図3.3.2.2−5は、1989年に起きた太陽フレア爆発の前後のTECの観測結果(小金井)で、北海道等でオーロラが観測された時期の前後の様子であり、大規模の撹乱(TECで前日の1/2以下に減少)のあと徐々に元に戻っていく様子がわかる。
(5)電離層遅延の補正
電離層遅延の大きさ、変化の概要等に関して、前節までに示した。GPS衛星の2周波信号により実測値で補正すること理想であり、特に、cm〜mmオーダーの精密相対測位では不可欠である。
一方、L1 C/A codeのみの利用者のためSA等の誤差要因を低減するため、実時間でのDGPSによる測位精度向上が一般利用に供されつつあるが、基準局との差分により電離層遅延に関しても補正が可能になるため、直接電離層遅延自体を評価しなくてもある程度の補正が可能となる。
前ページ 目次へ 次ページ
|

|